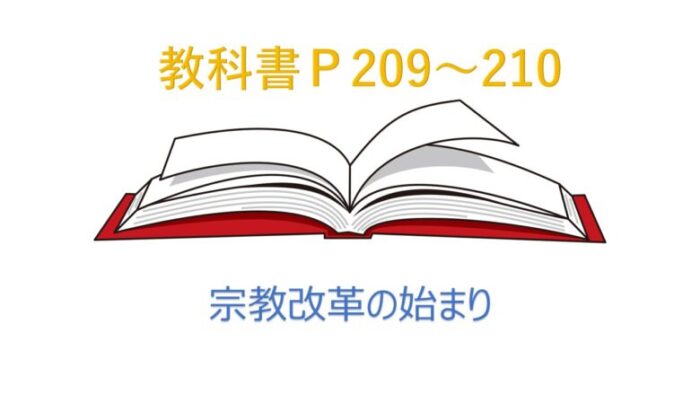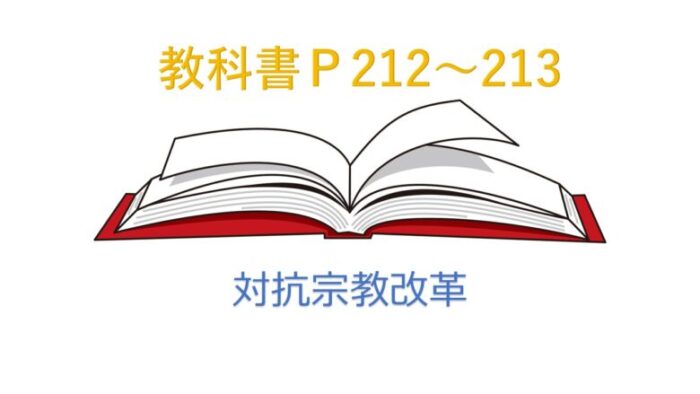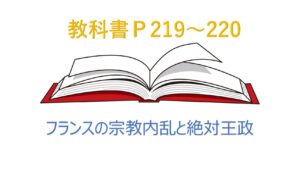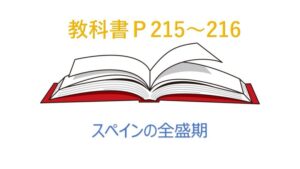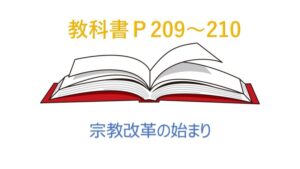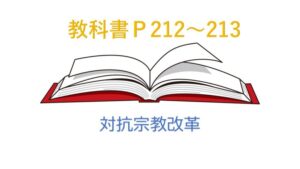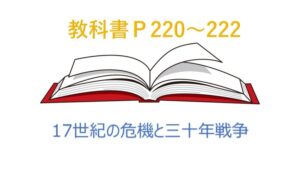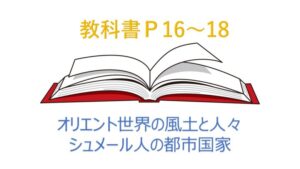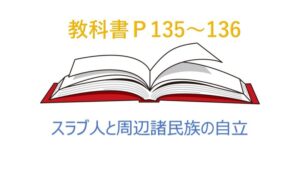詳説世界史B(改訂版) P211~P212 (山川出版社)
ここのページで書かれていることをざっくりまとめると・・・
ルター派と同じく旧教に異議を唱えたカルヴァン派が生まれるが、同じプロテスタントでもカルヴァン派はより厳格な禁欲主義および原理主義であった。また、イギリスでも独自のイギリス国教会が生まれ、キリスト教世界は新教と旧教が対立する時代に入っていく。
キリスト教世界が大きく変わる時代ですね。
宗教改革はルターが有名ですが、カルヴァンも後のキリスト教世界にとって大きな変化をもたらす人物です。
それでは、ルターが現れた後の、カルヴァン派登場の世界を教科書に沿ってみていきましょう。
カルヴァンが唱えた予定説
ツヴィングリ
スイスでは、ツヴィングリがチューリヒで宗教改革を開始したが、その後、フランスの人文主義者で「キリスト教綱要」を公刊したカルヴァンがジュネーヴで独自の宗教改革をおこなった。彼の教えの特徴は、神の絶対主権を強調する厳格な禁欲主義で、ジュネーヴでは一種の神権政治がおこなわれた。
詳説世界史B(改訂版):山川出版社
教会批判のはじまりは、14世紀後半のイギリス、ウィクリフという人物からです。
彼は聖書をラテン語から英語に訳し、また、カトリック教会のあり方や贅沢な暮らしをしている聖職者たちに疑問をもち批判をしました。
ラテン語って、一般の人には読めない言語です。
貴族でも読める人は限られています。
さらに、今のように聖書が本として誰もが手に取れるものではありません。
つまり、聖書は聖職者たちの特権であったわけで、無知な人たちをコントロールできる点でものすごくおいしい(?)ものなわけです。(聖書に書かれていないことを伝えたとしても、バレないってことです)
そんな聖書を、イギリス内で普段人々が使っている英語に訳すとなると、理解出来る人が増えるわけですね。
こういうものが広がると、教会、聖職者たちは焦るわけです。
話がそれました。。。
さて、ウィクリフの次にはベーメン(ボヘミア、後のチェコ)でヤン・フスが登場し、贖有状を批判します。
そしてルターが現れ、活版印刷の普及と時代が相まって爆発的に宗教改革の流れが大きくなります。
そんな中で、スイスにツヴィングリが現れるのです。
ルターとツヴィングリが生きた時代は同じです。
ツヴィングリはルターの宗教改革に強く影響を受けます。
がしかし、ルターのやり方はまだまだ生ぬるいと言い、同じようにカトリックにたいしては批判するものの、ルターとツヴィングリもまた、お互い相容れません。
ツヴィングリはより厳格に聖書に従った生き方を主張し、一切の妥協を許しません。
そんなもんだから、うまく味方を見つけて生き続けたルターとは対照的に、ツヴィングリは戦死します。
カルヴァン
カルヴァンは、魂が救われるかどうかは、あらかじめ神によって決定され ているという「予定説」を説いたが、これが職業労働を神の栄光をあらわす道と理解する考えと結びついて、西ヨーロッパの商工業者のあいだに広く普及した。教会組織のうえでは、ルターが司教制度を維持したのに対し、カルヴァンはこれを廃止し、教会員のあいだから信仰の厚いものを長老に選び、 牧師を補佐させる長老主義を取り入れた。
詳説世界史B(改訂版):山川出版社
ツヴィングリに集まって活動していた信者たちをうまく吸収したのがカルヴァンです。
彼もまた、徹底的な聖書至上主義でしたが、ツヴィングリほどはヤバくなかったのでこの後カルヴァン派は多くの地域に広がっていきます。
とはいうものの、ツヴィングリから続く神権政治はカルヴァンも行います。
具体的には、正しい信仰生活をしているか夜回りをしてチェックするのです。
トランプ遊びはだめ、夜に音楽を聴くのはだめ、娯楽はもってのほか、質素に生活しひたすら神に与えられた職をまっとうせよ、というように細かいことをすべて決めて、守られているかをみて回ったのです。
守られていなとわかれば容赦なく捕らえます。
そして火炙りにしてしまうのです。
そんなバカな・・・と思うのですが、これがカルヴァンによる神権政治という名の恐怖政治でした。
カトリックだけでなくルター派などのプロテスタントにも行っていたのですからかなり徹底していたようです。
よくもまぁ、カルヴァン派というのが生き残ったなと思いますね。
さて、カルヴァン派の一番の特徴は「予定説」です。
予定説
人間は、生まれたときから天国にいくのか地獄にいくのか決まっている。この世のすべては神が定めており、人間の意思で変えることはできない。
つまり、人間の意思なんて関係ない、神がすべてという徹底的な原理主義です。
一方で、禁欲・勤勉な生活をした結果得られる蓄財は肯定されたため、これが後に資本主義社会を作ることとなったとも言われています。
神が定めた仕事を頑張った結果得られたものは、神が与えてくれたものだから問題ない、てことですね。
| カトリック | 聖書と伝承重視 | イタリア、フランス、スペイン、ドイツ南部等 |
| プロテスタント(ルター派) | 聖書至上主義 | ドイツ北部、スウェーデン、デンマーク等 |
| プロテスタント(カルヴァン派) | 予定説 | オランダ、アメリカ |
| プロテスタント(イギリス国教会) | 教義はプロテスタント 儀式はカトリック | イングランド |
カルヴァン派は、16世紀後半にはフランス・ネーデルラント・スコットランド・イギリス(イングランド)などにも広まり,ドイツや北欧諸国で有力で あったルター派とならんで、もはや無視できない キリスト教の宗派となった。 新教徒 (プロテスタント)ということばは、これらローマ教皇の権威を認めず、聖職者の特権を否定する (万人司祭主義)宗派の総称になった。
詳説世界史B(改訂版):山川出版社
ちなみに、カルヴァン派は地域により以下の呼び方で教科書に登場します。
- フランス:ユグノー
- イングランド:ピューリタン
また、現代もみておきましょう。
現代の代表的なカルヴァン派の国は、アメリカ、スイス、オランダなどです。
ルター派の国は、ドイツ北部、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドの北欧あたりが中心です。
イギリス国教会の誕生
イギリスでは、国王ヘンリ8世がスペイン王家出身の王妃との離婚を認めようとしない教皇と対立して、宗教改革が始まった。彼は1534年の国王至上法(首長法) で国王がイギリス国内の教会(国教会)の首長であると宣言してカトリック世界から離脱し、 さらに修道院を議会立法で廃止して、その広大な土地財産を没収した。 しかし、教義面の改革がすすんだのは長男のエドワード6世の治世であった。 つぎの女王メアリ1世はスペイン王室と結んでスペイン王室と結んでカトリックを復活しようとくわだてたが、エリザベス1世の治世になって、1559年の統一法でイギリス独自の教会体制が最終的に確立した。イギリス国教会は、ほぼカルヴァン主義を採用しているが、司教(主教)制を維持するほか、儀式の面でも旧教に似かよった点を残しているため、ピューリタン(清教徒)と呼ばれた人々はカルヴァン主義をより徹底することを求めた。
詳説世界史B(改訂版):山川出版社
ちょっと変わった形でカトリックから離脱したのは、イギリスでした。
国王ヘンリ8世が、カトリックで禁止されている離婚を主張したため、最終的にイギリス国教会をたちあげました。
カトリックからの離脱を宣言。
もちろん、ローマ教皇から破門されます。
詳しくはこちら

イギリス国教会はカルヴァン派として成立するのですが、教義はカルヴァンでや儀式はカトリックのままだったりと、中途半端な状態です。
それが後にピューリタンたちの反感をかい、彼らはアメリカ大陸に渡るのですが。
それはまた別の話として、イギリス国教会が安定するのには少し時間がかかりました。
ヘンリ8世ののち、メアリ1世の治世ではカトリックに戻そうとする動きがでました。
詳しくはこちら

しかしその後エリザベス1世の治世でイギリス国教会は盤石なものとなりました。
彼女に取り入ろうと、周りのヨーロッパ国王たちは結婚を申し込みますが、エリザベス1世は結婚により他国の干渉を受ける可能性を嫌ったのでしょう。
彼女は生涯結婚せず、処女王と呼ばれることとなった所以です。
愛人はたくさんいたそうですが。
教科書の前ページ、次ページはこちら